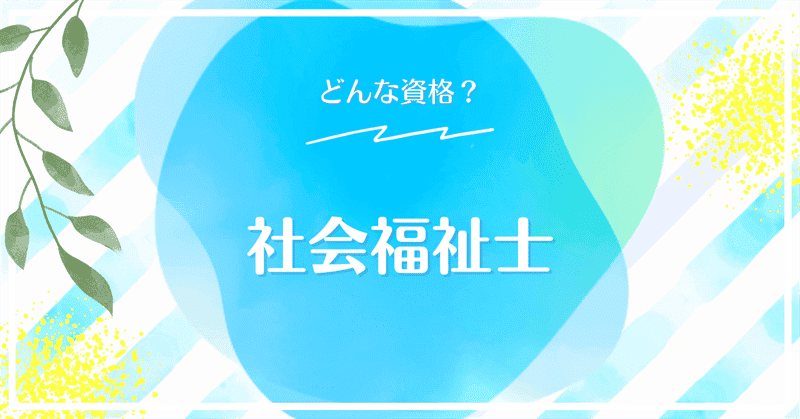
- 初任者研修とは?
- > 【2025年(令和7年)】社会福祉士とはどんな資格?仕事内容や資格取得方法、難易度などを解説!
【2025年(令和7年)】社会福祉士とはどんな資格?仕事内容や資格取得方法、難易度などを解説!
社会福祉士は、病気や障害、貧困などで生活に困っている人たちを支援する仕事です。
少子高齢化や子どもの虐待、貧困などの増加とともに、社会福祉士のニーズは高まっています。
この記事では、以下のポイントを紹介します。
記事を最後まで読むと、社会福祉士になる方法や仕事内容など、社会福祉士の全体像が掴めます。社会福祉士を目指している方や興味をお持ちの方は、ぜひ最後までご一読ください。
社会福祉士とは?概要を紹介!

社会福祉士とは、1987年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき、福祉や医療に関する相談援助に必要な専門知識・スキルがあることを証明する国家資格です。
資格を取得し申請すると、厚生労働大臣より社会福祉士登録証が交付されます(法第28条)。
身体及び精神に障害のある方、生活困窮者、ひとり親の家庭など、心身や環上の理由によって日常生活を送るのに支障がある方々の相談援助をおこないます。
高齢者から子供まで幅広いこともあって、活躍の場も多岐に渡っているほか、高齢化や近年の虐待問題増加の影響もあり、ますます社会福祉士への期待は高まっていくと予想されます。
社会福祉士は、社会的ニーズの広がりを見せている注目の資格といえるでしょう。
※出典元:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
資格取得には、社会福祉士国家試験に合格する必要があります。
過去問やテキストを使って独学で試験勉強をする以外にも、スクールの試験対策講座を受講する方法があります。費用はかかりますが、より確実に合格を目指したい方は受講検討してみるのもよいでしょう。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士とはどんな仕事をするの?

主な仕事は相談業務
社会福祉士の主な仕事は「相談業務」です。身体的・精神的な障害を持つ方や環境上の理由から日常生活を送るのが困難な方の相談にのります。社会福祉士は保険・医療、高齢者福祉、障害者支援、生活保護、児童福祉など、福祉に関するすべての相談を受けるので、福祉に関する幅広い知識が必要です。
そして、相談内容をもとに一人ひとりに合った公的支援制度や福祉サービスを提案し、行政機関や医療機関と相談者との橋渡しをすることも社会福祉士の大切な仕事の1つです。
また、介護施設などで働く社会福祉士のなかには、相談業務だけでなく実際の介護業務にも携わる方が多いです。
社会福祉士の主な就業先
社会福祉士のサポートを必要としている人は高齢者から子ども、障害者など幅広いです。
そのため職場の種類も多く、高齢者施設や児童相談所、医療機関など様々な働き口・働き方があります。
公務員として役所の福祉課などで働くことも可能です。
詳しくは『社会福祉士の就職先は?社会福祉士の資格を活かせる仕事や求人例を一挙紹介!』にまとめていますので、参考にしてください。
社会福祉士資格を取得するメリットは?
社会福祉士は『福祉・医療に関する相談援助の専門家として認められた国家資格』です。
資格が無くても福祉や医療に関する相談援助の仕事をすることはできますが、社会福祉士資格を持っていれば専門家としての社会的な信用性も高く、選考時にも優位に立てるでしょう。また、相談者からも信頼を得られるはずです。
尚、社会福祉士は国家資格のなかで名称独占資格にあたり、資格を持っていないと社会福祉士を名乗ることができません。
そのため、資格を持つことで専門知識があるかどうかの証明にもなります。また、職業名は「ソーシャルワーカー」や「生活相談員」などと呼ばれています。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士の1日の流れ
勤務先により1日の流れは異なりますが、参考になれば幸いです。
地域包括支援センターで働く社会福祉士の勤務スケジュール例
地域包括支援とは、高齢者が自分らしい生活が送れるように支援するしくみです。医療や保険、福祉などの観点から、包括的に高齢者を支える施設として各市町村に設置されています。
地域包括支援センターの社会福祉士・1日の流れ
| 8:30〜 | 出勤。朝礼で前日からの申し送りや注意事項などを受ける |
| 9:00〜 | 担当高齢者の自宅へ訪問相談 |
| 11:00〜 | デイサービス利用希望者の相談電話を受ける |
| 12:00〜 | 昼休み |
| 13:00〜 | 行政機関との定例会議 |
| 15:30〜 | 担当高齢者の利用施設で訪問相談 |
| 17:30 | 退勤 |
地域包括支援センターの社会福祉士は、担当高齢者の自宅や施設に訪問したり、行政機関との打ち合わせなど、外出を伴う業務が多いという特徴があります。
「オフィスでずっと働くのは気づまり」「いろいろな所に外出して人と話したい」という人に向いている職業と言えるでしょう。
医療機関で働く社会福祉士の勤務スケジュール例
医療機関で働く社会福祉士は、急性期病棟や慢性期病棟、リハビリ病院、クリニックなどさまざまな場所で活躍しています。
医療機関の社会福祉士・1日の流れ
| 8:30〜 | 出勤。打ち合わせで申し送りを受ける。メールの返信確認 |
| 9:00〜 | 受け持ち患者のカルテを確認、相談支援の計画を立てる |
| 10:30〜 | 市町村の福祉センター等と合同で地域活動 |
| 12:00〜 | 休憩時間 |
| 13:00〜 | ケアマネと打ち合わせ。病棟を回って多職種と意見交換 |
| 14:30〜 | 療養中の高齢者の経済問題の相談にのり、調整援助 |
| 16:30〜 | その日の出来事を振り返り、カルテ入力 |
| 17:30 | 退勤 |
医療機関で働く社会福祉士は、患者の病気の経過を医療スタッフと連携しながら把握し、退院に向けたサポートなどを行います。
医療スタッフだけではなく、ケアマネジャーや福祉センターの職員など、他職種と連携する必要もあるため、コミュニケーション力の高い人に向いていると言えます。
介護老人福祉施設で働く社会福祉士の勤務スケジュール例
介護老人福祉施設で働く社会福祉士は、短期入院施設(ショートステイ)や通所介護施設(デイサービス)に入退所する高齢者の相談を受けるのが主な仕事です。
介護老人福祉施設の社会福祉士・1日の流れ
| 8:30〜 | 出勤。朝礼にて介護士からの申し送りや伝言、本日の注意事項などを受け取る |
| 9:00〜 | 入居相談者宅を訪問。相談内容を聞き、アセスメントを実施 |
| 11:00〜 | 休憩時間 |
| 12:00〜 | 介護スタッフとともに入所者の食事を介助 |
| 13:30〜 | 新規の入所予定者の支援計画書や相談者との面談 |
| 16:30〜 | 退所予定者と退所後の住居を見に付き添い |
| 18:30 | 報告書などの書類作成し、退勤 |
介護老人福祉施設で働く社会福祉士は、新規入居者や退所者の相談以外に、介護を行うケースも多いです。介護の資格がある人や、介護に興味がある人が働きやすい職場と言えます。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士が支援するのはどんな人?
社会福祉士の仕事の範囲や対象は多岐にわたります。高齢者や障害者、母子家庭などの相談を受けて支援をします。
社会福祉士資格取得者が働く職場は社会福祉施設等が最も多く、その他社会福祉協議会、医療機関、行政機関、独立型社会福祉士事務所等が代表的なものです。
高齢者
| 対象 | 施設で暮らす高齢者、施設を利用する高齢者 |
| 職場 | 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、地域包括支援センターなど |
| 職種 | ソーシャルワーカー、生活相談員(指導員)など |
子ども
| 対象 | 障害児、保護者の養育を受けられない子ども、非行児童、およびその家族 |
| 職場 | 児童相談所、児童養護施設、障害児入所施設、母子生活支援施設、母子福祉センター、児童自立支援施設など |
| 職種 | 児童福祉司、児童指導員、母子相談員、少年指導員、児童自立支援専門員など |
障害者
| 対象 | 障害者、およびその家族 |
| 職場 | 障害者支援施設など |
| 職種 | 生活相談員(指導員)、作業指導員など |
生活に困っている人
| 対象 | 母子家庭、失業者、生活困窮者など |
| 職場 | 福祉事務所など |
| 職種 | 現業員(ケースワーカー)、査察指導員(スーパーバイザー)、専門職員など |
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士になるには?資格の取得方法
国家試験合格が必須!
社会福祉士資格を取得するには、年1回(2月上旬頃)実施される国家試験に合格しなければなりません。
また、受験するには学歴や実務経験などによって受験資格が決められています。社会福祉士国家試験を受けようとお考えの方は、まずはじめに受験資格があるかないかの確認が必要です。
社会福祉士のなり方や資格取得方法について詳しくは『社会福祉士になるには』で解説していますので、参考にしてください。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士国家試験の受験資格や指定科目
社会福祉士試験の受験資格取得ルートは12種類
社会福祉士を受験するためには12通りの資格取得ルートがあります。
自身がどのルートに当てはまるのかあらかじめ確認し、受験するまでのスケジュールをイメージしておきましょう。
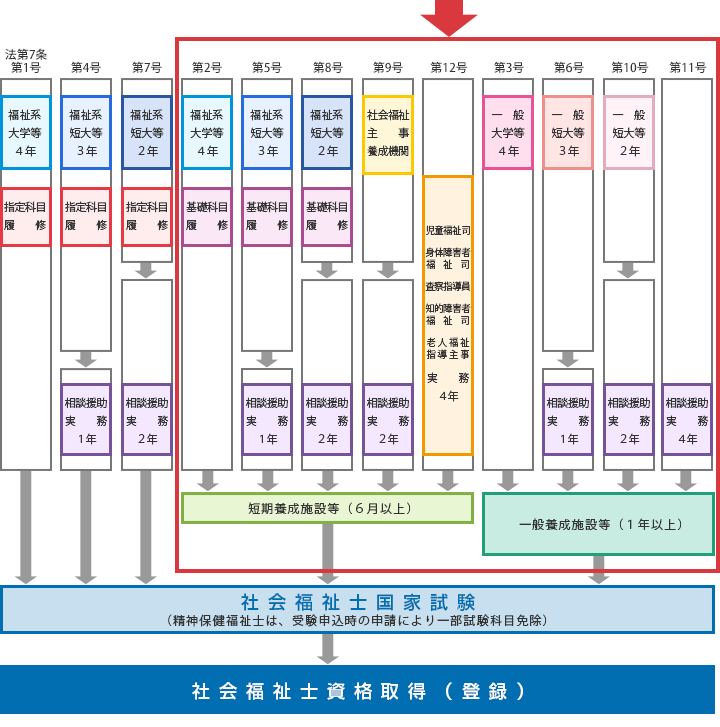
※引用元:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」
一般の4年制大学を卒業している場合は、一般養成施設などでカリキュラムを1年以上履修すれば、社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。
一般の短大卒業の場合、一般養成施設等での1年以上のカリキュラムを履修する前に、3年制は1年、2年制は2年の相談援助実務経験が必要です。
受験資格の満たし方など詳しくは『社会福祉士になるには?受験資格や最短での資格取得ルート、おすすめの勉強法などについて解説!』で解説していますので、どのルートに該当するのか確認してみてください。
社会福祉士試験の受験指定科目
社会福祉士国家試験は、全19の指定科目(19科目群)と範囲が広いという特徴があり、計画的に試験対策をすすめていく必要があります。
以下に、社会福祉士試験の19の指定科目を紹介します。
- 人体の構造と機能及び疾病
- 心理学理論と心理的支援
- 社会理論と社会システム
- 現代社会と福祉
- 地域福祉の理論と方法
- 福祉行財政と福祉計画
- 社会保障(7問)
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 低所得者に対する支援と生活保護制度
- 保健医療サービス
- 権利擁護と成年後見制度
- 社会調査の基礎
- 相談援助の基盤と専門職
- 相談援助の理論と方法
- 福祉サービスの組織と経営
- 高齢者に対する支援と介護保険制度
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
- 就労支援サービス
- 更生保護制度(4問)
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士国家試験の合格率や難易度
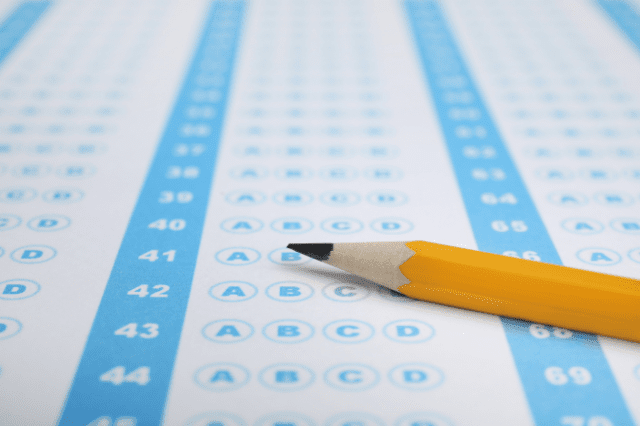
社会福祉士試験の合格基準や合格率
合格基準点は正答率60%の90点です(難易度による補正あり)。
総得点が合格ラインを超えていても、19の指定科目のうち0点の科目群が1つでもあると、不合格になります。
2024年(令和6年)第36回社会福祉士国家試験の合格率は58.1%です。
受験資格別では、福祉系大学等卒業者が約56%、短期養成施設の卒業者が約44%となっており、福祉系大学卒業者の合格者数がやや多いです。
過去データをみると、合格率はおよそ30〜40%程度で推移しています。
過去データについては『社会福祉士国家試験の合格点と合格率は?難易度についても解説!』で紹介していますので、参考にしてください。
社会福祉士試験の難易度は高い!
社会福祉士試験は、福祉系国家資格のなかでは最も難易度が高いと言われています。
福祉系国家試験の合格率は以下の通りです。
| 資格 | 合格率 |
|---|---|
| 社会福祉士 | 30〜40%程度 |
| 介護福祉士 | 60%〜70%程度 |
| 精神保健福祉士 | 60%程度 |
| ケアマネジャー | 10%〜20%程度 |
社会福祉士の合格率が低い最大の理由として、出題範囲の広さが挙げられます。
専門用語や制度が登場する指定科目も多く、覚えるべき知識は膨大です。
また、試験科目の多さから学習時間が不足してしまう点も合格率が低い理由の一つです。
社会福祉士に合格するためには300時間の勉強時間が必要とされていますが、学校や短期養成施設に通いながら学習時間を確保することは非常に困難といえるでしょう。
また、受験者の半数以上は社会人として働きながら受験勉強に励んでおり、受験日までに合格レベルまで到達できないことも合格率に影響していると考えられます。
そのため、各スクールが開講している試験対策講座を受講し、効率よく勉強する方法が有効でしょう。
合格率が低い理由や一発合格率を上げるためのポイントについては『社会福祉士国家試験の合格点と合格率は?難易度についても解説!』で紹介していますので、参考にしてください。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士を目指す人によくある疑問
- 社会福祉士の年収は高い?
- 社会福祉士は仕事がないって本当?
- 社会福祉士と介護福祉士の違いとは?
- 社会福祉士の受験資格が変わるってホント?
- 社会福祉士の免許は通信だけで取れる?
- 社会福祉士国家試験の概要
社会福祉士の年収は高い?
社会福祉士の資格を持つ職員の平均年収は403万円です。日本の平均年収と比較すると低い傾向にあります。
2020年度(令和2年度)に行われた社会福祉振興・試験センターの調査によると、福祉・介護・医療分野で就労している社会福祉士の平均年収は403万円でした。 男女別に見ると、男性で473万円、女性で365万円となっています。
詳しくは以下ページで紹介しています。
>> 社会福祉士の年収・給料はどれくらい?年収アップの方法についても解説!
社会福祉士は仕事がないって本当?
高齢者や障害者など、社会福祉士を必要とする人は多いため、社会福祉士の仕事は数多くあります。
それにもかかわらず「仕事がない」という噂を耳にした方もいらっしゃるでしょう。
社会福祉士は、資格を取得しただけでは仕事をスムーズに進めるのが難しい職業です。
資格を取得して施設や事務所に就職し、長い実務経験を積んでようやく仕事ができるようになるのです。それまでは離職せずに粘り強く自分磨きをする必要があります。
途中で挫折して離職してする人も多いので「仕事がない」と言われてしまうようです。
社会福祉士の就職先については以下ページで紹介しています。
>> 社会福祉士の就職先は?社会福祉士の資格を活かせる仕事や求人例を一挙紹介!
また、求人のなかには「未経験」でも募集・採用しているケースもあり、詳しくは以下ページで紹介しています。
>> 社会福祉士に「未経験可」の求人はある?未経験でも採用されるコツや求人例を紹介!
社会福祉士と介護福祉士の違いとは?
社会福祉士の仕事は、福祉の現場で支援が必要な人が利用できるサービスを紹介するなど、相談者が快適な生活を送れるようにアドバイスすることです。
一方、介護福祉士の仕事は、介護施設や訪問介護などで、介護が必要な人に介護サービスを提供することです。
社会福祉士の受験資格が変わるってホント?
すでに社会福祉の受験資格は2013年度(平成25年度)に変更されています。
もともと社会福祉士試験の資格は、次のような実務を5年積めば受験資格を得られました。
児童福祉司
身体障害者福祉司
福祉事務所の査察指導員
知的障害者福祉司
老人福祉指導主任
しかし、2013年度(平成25年度)の第26回試験からは、実務経験4年以上に加え、6ヶ月以上の養成課程を修了しなければ受験資格を得られなくなりました。
受験資格の満たし方など詳しくは以下ページで紹介しています。
>> 社会福祉士になるには?受験資格や最短での資格取得ルート、おすすめの勉強法などについて解説!
社会福祉士の免許は通信だけで取れる?
社会福祉士の資格は、通信講座だけで取得するのは難しいです。
福祉系大学や短大を卒業していればそのまま受験可能ですが、それ以外の場合は、福祉系大学や短大に入学する、実務経験を積む、短期養成施設に通うなどが必須です。
通学する時間が少ない場合は、通信+通学コースのある通信講座を選んだり、通信大学や短期養成コースのある専門学校を選ぶとよいでしょう。
詳しくは以下ページで紹介しています。
>> 通信講座で社会福祉士の資格は取得できるの?おすすめの通信制大学や養成施設を紹介!
社会福祉士国家試験の概要
受験資格がある方は、申し込み期間内に受験手続きを行う必要があります。申し込み期間を過ぎてしまうと受験することができません。間に合わずに受験できない、なんてことが無いよう余裕を持って手続きすることをおすすめします。
2023年度(令和5年度)の試験日程:
2024年(令和6年)2月上旬
2023年度(令和5年度)の申し込み時期:
2024年(令和6年)9月上旬から10月上旬
最新の試験情報、過去実施試験の合格率や難易度傾向など、詳しくは以下ページで紹介していますので参考にしてください。
>> 【最新】試験概要とスケジュール
>> 試験難易度と合格ライン
>> 【最新】社会福祉士国家試験の正式解答
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士からキャリアアップを目指せる!

相談援助関連の資格取得する際も有効!
社会福祉士資格を持っていれば、ほかの相談援助関連の資格取得をする際にも有効です。
◎精神保健福祉士(国家資格)
社会福祉士と精神保健福祉士の試験には、共通科目があります。
社会福祉士資格を持っていて、短期養成施設等で精神保健福祉士養成課程を修了し共通科目の受験免除申請をすれば、共通科目が免除されます。
精神保健福祉士資格試験を受験しやすくなりますね。
類似点は多くありますが『相談援助の対象者』『習得できる専門知識』などの違いがあります。
◎社会福祉主事(任用資格)
国家資格以外で生活相談・援助に関する資格として、社会福祉主事(任用資格)があります。任用資格とは『特定の職業ないし職位に就いた際に効力を発揮する資格』を指します。
資格取得の要件はありますが、社会福祉士資格を取得すれば要件を満たしていることになります。
尚、社会福祉主事のほかにも生活相談・援助の任用資格で『児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司』などがあります。こちらも社会福祉士資格があれば、資格要件を満たしていることになります。
相談援助事業所の独立開業も目指せる!
社会福祉士資格を取得後、独立型社会福祉士として開業することができます。
さらに『公益社団法人 日本社会福祉士会』の独立型社会福祉士名簿に登録することで、社会的信用及び認知を確保でき独立型社会福祉士同志のネットワークにも入ることができます。
【名簿登録者数:2020年4月27日時点で452名】
事業所などでは限られた相談者への対応になりますが、独立開業した場合には自分自身で幅広くできるようになりますね。
ただし、独立型社会福祉士名簿に登録するには必要要件がいくつかあります。
◎主な必要要件
- 都道府県社会福祉士会の会員であること
- 認定社会福祉士認証・認定機構が認定した『認定社会福祉士』であること
- 独立型社会福祉士に関する研修を修了していること
※「独立型社会福祉士の新名簿登録制度の概要」より抜粋
『認定社会福祉士』になるためには、社会福祉士資格取得後に相談援助業務5年以上、かつ認定分野で2年以上の経験、認定研修の受講・修了が必要です。時間はかかりますが、独立開業したい方は実務経験を積みながら検討してみるのもよいでしょう。
資格取得で特別養護老人ホームの施設長も目指せる!
社会福祉士の資格の取得など、厚生労働省老健局の定める要件を満たすと、特別養護老人ホームの施設長になることができます。施設長に就任できると、給与アップの可能性もあります。
介護職員として働いていてキャリアアップをしたい方は、資格取得を目指してみるのもよいかもしれません。
◎給与相場
- 社会福祉士の実務経験2年の場合:年収350万円程度
- 特別養護老人ホーム施設長:年収350万円〜700万円程度
※勤務先や経験年数などよって異なる場合があります。
社会福祉士の上位資格「認定社会福祉士制度」も目指せる
社会福祉士資格は専門知識を有することを証明できる国家資格ですが、資格の取得要件に実務経験は必須ではありません(※資格取得ルートにより異なります)。
そのため、社会福祉士試験の合格だけでは、実践力を証明できません。
そこで、高度な知識と技術の証明となる社会福祉士の認定制度が設けられました。
認定社会福祉士を取得することは、社会福祉士としての実践力や専門性の証明となり、実力をクライアントや関係者に示せます。
社会福祉士としてさらにステップアップしていきたい方は、認定社会福祉士の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)社会福祉士試験で一発合格を目指すなら

スクール開講の試験対策講座受講がおすすめ!
受験資格を満たしている方は、試験に向けた準備が必要です。過去問題集やテキストなどを使って独学で受験対策をする方法もありますが、スクールでは試験対策講座も開講しています。過去問題集やテキストは3,000円程度に対して、試験対策講座は5万円程度です。
講座受講の方が割高ですが、疑問や質問に対してのサポートや試験日までの計画的な学習スケジュールが組まれるので、試験対策もスムーズに進められるのではないでしょうか。
また、試験の頻出問題や合格するためのコツ、受験生の声なども聞くことができるはずです。
自身でどのように進めてよいか分からない方、より確実に合格するための学習をしたい方には講座受講がおすすめです。
社会福祉士に興味をお持ちの方は、以下のボタンより複数のパンフレットを取り寄せて、講座を比較・検討されてみてはいかがでしょうか。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)【おすすめスクール】
日本医療大学 通信教育部では、「オンデマンド学修」が主体でインターネットでのeラーニング活用により、ご自身の好きな時間に学修を進めることが可能です。
スクーリングは札幌(本学)・仙台・首都圏で開催予定。
指定科目を履修して卒業すると、社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。
監修者について

藤島 薫(ふじしま かおる)
北海道千歳市生まれ
東京福祉大学社会福祉学部准教授。博士(社会福祉学)
専門:ソーシャルワーク、若者早期支援、プログラム評価(参加型評価)
福祉施設において介護業務、相談業務に従事。大原学園介護福祉士養成施設専任教員、旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科准教授を経て、現在に至る。
保有資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- ヘルパー2級資格
- ガイドヘルパー資格
- 幼稚園教諭1級
- 評価士(日本評価学会認定)
- CBTカウンセラー(旧:東京認知行動療法アカデミー認定)
- エンジョイ個育てファシリテーター(フィンランドブリーフセラピー協会認定)
著書
お問い合わせはお問い合わせメールまでお願いいたします。
※メールにてお問い合わせいただく際は、PCからのメールを受信できるように設定をご変更ください。
※スクールや講座については、直接スクールにお問い合わせください。
※試験情報・要綱に関しましては、最新の情報は各自治体・各主催団体の公式HPをご確認ください。
※お問い合わせ内容によってはご返信までに2〜4日いただきます。
社会福祉士の講座選びなら


BrushUP学びはスクールや学校、講座の総合情報サイト。
最安・最短講座や開講日程、分割払いなどをエリアごとに比較して無料でまとめて資料請求できます。
まずは近くのスクールを チェックしてみてくださいね♪
平日なら電話での請求も可能です。
\近所のスクール・講座をみてみる/
社会福祉士の講座を資料請求(無料)\最短1分!いろいろなスクールを比較できます/
社会福祉士の講座資料を請求(無料)- 社会福祉士 関連ページ
- 社会福祉士とは 社会福祉士になるには 社会福祉士の実習は必須?実習内容や実習免除の条件についても解説! 高卒で社会福祉士になるには?受験資格を得るためのおすすめルートも解説! 【2023年度(令和5年度)最新情報】社会福祉士試験とは 【2023年・第35回】社会福祉士国家試験の解答速報 社会福祉士の難易度と合格率・合格基準点 社会福祉士国家試験の勉強方法は?テキストや独学についても解説! 社会福祉士は通信講座で資格取得できるの? 社会福祉士の就職先は? 社会福祉士に求められる役割とは?職場による違いについて解説! 社会福祉士に「未経験可」の求人はある? 公務員として働ける社会福祉士とは? 社会福祉士の年収・給料はどれくらい?
- 介護資格 人気ページ
- 最短1ヶ月で介護職員初任者研修取得 一番安い初任者研修 一番安い実務者研修 介護福祉士のおすすめ通信講座 一番安いケアマネ講座と勉強法 一番安い介護事務講座 介護資格の種類と職業 介護従事者に学んでほしい講座一覧
